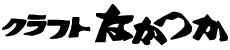伊賀焼

伊賀焼とは
 信楽をひと山越えると、そこが焼きものの里伊賀です。中世に始った伊賀焼は、陶土が信楽焼と同じなため、両者は殆んど区別されていなかったようです。
信楽をひと山越えると、そこが焼きものの里伊賀です。中世に始った伊賀焼は、陶土が信楽焼と同じなため、両者は殆んど区別されていなかったようです。天正の終わりに領主となった筒井定次や藤堂高虎、高次の時代、お庭焼として茶人の古田織部などの指導のもと、荒々しく美意識を持った茶陶の水指や花入が焼かれました。この時代を総称した古伊賀は「伊賀に耳あり、信楽に耳なし」といわれます。茶陶の水差や花生けは耳を持つものが多く残されているためです。
寛文の頃に、白土山の陶土濫掘防止のため衰退します。以降幾多の興亡を繰り返しながら、天保末期からその耐火耐熱度を活かした土鍋、行平などの生活雑器を量産し、現在に至ります。
特徴
 伊賀焼をつたえるには、特異な粘土の性質を述べるしかありません。古琵琶湖層と呼ばれる地層は、400万年前の生物や植物の遺骸が多く含まれる堆積層です。窯で焼成すると遺骸は細かな気孔になります。その気孔が蓄熱を生み、冷めにくい魔法のような土鍋になるのです。大地の恵といえます。
伊賀焼をつたえるには、特異な粘土の性質を述べるしかありません。古琵琶湖層と呼ばれる地層は、400万年前の生物や植物の遺骸が多く含まれる堆積層です。窯で焼成すると遺骸は細かな気孔になります。その気孔が蓄熱を生み、冷めにくい魔法のような土鍋になるのです。大地の恵といえます。この耐火性が高く、蓄熱性に富んだ土鍋は他にはありません。また歴史が積み重ねた経験値で、土鍋の厚みや形状が作られています。一度使うと手放せない、そんな調理具を作っているのが伊賀の里にあります。
窯元紹介
 伊賀の長谷製陶は、天保3年に伊賀丸柱の地に築窯し7代目となります。当主の長谷優磁さんは、おシャレでアイディアのすごい方です。食べることがお好きなようで、次々と素材に応じた土鍋を考え出してくれます。しかも全てが、伊賀の粘土の特性を生かすもの。
伊賀の長谷製陶は、天保3年に伊賀丸柱の地に築窯し7代目となります。当主の長谷優磁さんは、おシャレでアイディアのすごい方です。食べることがお好きなようで、次々と素材に応じた土鍋を考え出してくれます。しかも全てが、伊賀の粘土の特性を生かすもの。食いしん坊では負けないのですが、ここの土鍋は外せません。しかも難しい火加減とか要領を気にしなくても、ちゃんと美味しくなります。伊賀を知り尽くした、陶工の秀作です。