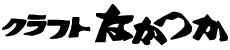益子焼

益子焼とは
 益子焼は江戸末期の嘉永、笠間で修業した大塚啓三郎が窯を築いたところから始まりました。行ってみると案外近く、電車は不便ですが自動車で30分程です。羽黒潘の庇護を受け5〜6軒の窯がカメ・火鉢・壺といった日用品を作っていたようです。粘が荒く精巧なものを作るには向かなかったのでしょう。
益子焼は江戸末期の嘉永、笠間で修業した大塚啓三郎が窯を築いたところから始まりました。行ってみると案外近く、電車は不便ですが自動車で30分程です。羽黒潘の庇護を受け5〜6軒の窯がカメ・火鉢・壺といった日用品を作っていたようです。粘が荒く精巧なものを作るには向かなかったのでしょう。ただ東京という大消費地に近いため、明治以降は着実に発展しました。またガスの普及という近代化の波で、庶民も金属の鍋釜を使うようになり、危機を向えたこともあったようですし、関東大震災の後は、いくら作っても追いつかない時期もりました。そうした時代を超えて現在に至っています。
転機は濱田庄司の定住ではないでしょうか。民芸運動を勧めた氏の影響を受け、台所から芸術性へと産地が変わって行きました。東京に近いがゆえに自在に進化する。それが益子焼ではないでしょうか。
(写真は濱田庄司記念館)
特徴
 益子焼の特徴は、粘土の耐火性のように思います。何度か轆轤を引いたことはあるのですが、例えば壺の口を成形する時は、思いよりも上に長く作り下に折り返し、厚くしっかりするよう教えて頂きました。火に弱いからとのこと。それが故に、ポッテリと手に優しい暖かいものが出来るのでしょう。
益子焼の特徴は、粘土の耐火性のように思います。何度か轆轤を引いたことはあるのですが、例えば壺の口を成形する時は、思いよりも上に長く作り下に折り返し、厚くしっかりするよう教えて頂きました。火に弱いからとのこと。それが故に、ポッテリと手に優しい暖かいものが出来るのでしょう。また釉薬も柿釉や飴釉といった、生地に良くあうものが多くあります。施釉も厚くしっかりとしています。この三つが揃って、益子の 焼のイメージが作られているようです。
こうしたところからも、濱田庄司の影響を強く感じますし、現代の感覚を磨きながら変わり続けていると思います。
窯元紹介
 現在219軒の(平成27年)窯元があります。その多くは個人窯です。たぶん日本で一番たくさんの方が作陶しています。そのため多様性にあふれ、昔をご存知の方には「これぞ益子焼」と「これが益子焼?」が混在しています。小鹿田焼などとは対極と言えるでしょう。
現在219軒の(平成27年)窯元があります。その多くは個人窯です。たぶん日本で一番たくさんの方が作陶しています。そのため多様性にあふれ、昔をご存知の方には「これぞ益子焼」と「これが益子焼?」が混在しています。小鹿田焼などとは対極と言えるでしょう。また外部の方が築窯しやすい土地柄でもあります。地理的なことも強く影響し、より消費者に寄り添ってゆくようです。薄く軽く益子の土や素材にこだわらず、以前の益子焼から遠くなってゆくのも仕方の無いことだと思います。